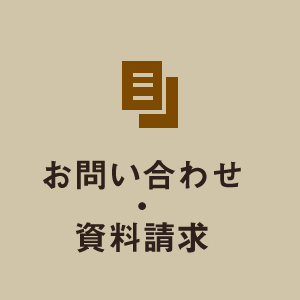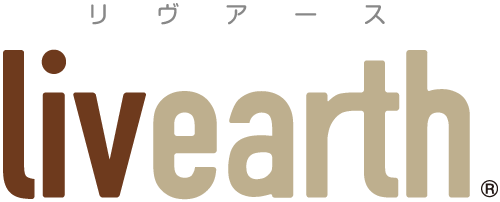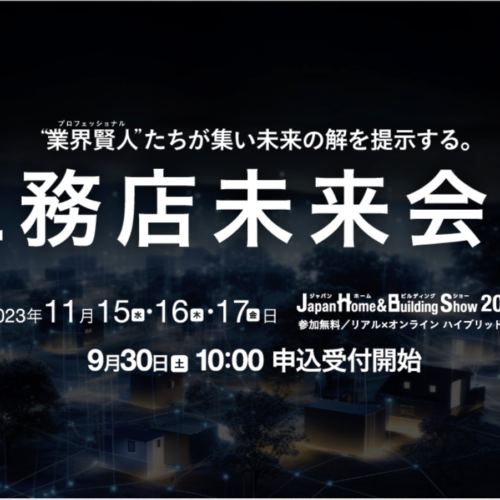建物における放射熱の影響
2015.11.29 カテゴリ:未分類
表面温度6000度の太陽の放射をマイナス273度の宇宙空間を介して、放射熱を受け続ける地球。
太陽の光のごく一部の波長である8~14μmの遠赤外線を利用することで生命活動を維持する人類。
日本の省エネ基準は、熱の対流による熱移動のみを対象にしていますので、放射の影響をほとんど評価できません。
参考【熱の伝わり方の3種類】
①伝導:物質を通して熱が伝わること。例)フライパンで料理するときの熱の移動。
②対流:空気や液体などの流れによって熱が伝わること。例)エアコン、ファンヒーターなど。
③放射(輻射):遠赤外線などの熱線によって直接、熱が伝わること。空気が無くても伝わる。例)太陽の熱、電気ストーブなど。
放射熱による熱移動、素材の熱容量の大小による蓄熱効果など重要な要素を考慮したかたちになることで、高断熱化した先にあるものが見えてくると考えます。
放射熱による熱の移動が評価出来るようになると、壁の厚みを遙かにこえる分厚い断熱材の厚みを取らなくてもよくなり、夏も高断熱化の末に訪れる高断熱の家は低断熱の家よりも室温が厚くなると言う現象を防ぐことが出来ます。
ドイツでは、すでに放射による熱の移動の評価が始まっているようです。